- トップ
- 代表・講師
- アクセス
- マンション管理士の活動
- マンション管理講座
- マンション管理・相談事例等
- 講習会等の日程
- ☆ 令和6年度補償業務管理士試験対策講座等のご案内
- 補償業務管理士試験対策講習会の目的
- その他
- 土地収用法基礎講座(1 任意取得と強制取得)
- 収用事例(収用の現場からのレポート)
- ☆ 「令和7年度版 補償業務管理士試験(共通科目)の分野別解説テキスト」・【CPD「e・ラーニングシステム」学習用コンパクト版】の発売
- 「補償業務管理士試験(共通科目)の過去問の分野別解説テキスト」の学習方法
- 「補償業務管理士試験(共通科目)の分野別解説テキスト」の『 Q&A 』
- 令和7年度共通試験解説講座(損失補償基準の体系について)
- 「令和7年度 共通試験対策基礎講座」
- 「令和7年度 一般補償基準・基本講座(測量士さんのための基礎講座)」
- 「令和7年度 補償業務管理士試験(共通科目)・試験対策 (令和6年度・本試験・解答掲載)」
- 令和7年度共通試験解説講座(補償業務管理士試験・共通科目の過去問の解説等のYouTube一覧表)
東山の森不動産・補償コンサルタント
東山の森不動産・補償コンサルタント
補償業務管理士試験(共通科目)の分野別解説テキスト・
CPD「e-ラーニングシステムの問題と解説」
の発売
(1)平成20年度~令和4年度分までの過去問解説テキストを発売中
(2)令和5年(本年)度本試験問題(共通科目・単年度版)の解説(データ配信)を発売中
(3)CPD 「e-ラ-ニングシステム」学習用コンパクト解説版(発売中)
補償業務管理士試験(共通科目)の分野別解説テキスト・【CPD 「e・ラーニングシステム」学習用コンパクト版】等の発売
(1)補償業務管理士試験(共通科目)の過去問(平成20年~令和6年)の分野別解説テキスト
但し、平成24年~R4年度分はテキストの送付、
平成20年~23年度及び令和5~6年度分は、データで配信
価格 : 6,000円 + 郵送料:500 計6,500円
(コンパクトな解説。各肢の解説の後に類似過去問が明示されており、過去問学習が容易で、出題傾向もわかりやすいです。)
(発 売 中)
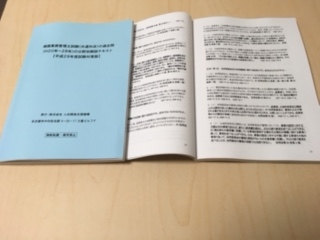
(2)令和6年度(本年度)「補償業務管理士試験(共通科目)の問題と解説」(※令和6年度分のみの解説):データで配信
価格 : 2,000円(A4版35P )
(コンパクトな解説。類似過去問との対比が容易で、
出題傾向がわかりやすい。)
(3)【CPD 「e・ラーニングシステム」学習用コンパクト版】
第3回(e試験1~6)~第9回(e試験1~6)の解説集発売中
1回分価格 1,500円(+郵送料500円)
数回分価格 1,500円×回数分(+郵送料500円)
4回分以上の価格 6,000円(+郵送料500円)
発 行 : 〒465-0077
名古屋市名東区植園町1-53-1
東山の森不動産・補償コンサルタント
支払い : 三菱UFJ銀行 星ヶ丘支店
【振込先】 (普通)1720767 森正隆
(支払い確認後、発送します)
申込み先 :下記までメール又は電話で申込みください
東山の森不動産・補償コンサルタント 代表 森正隆
TEL: 052-782-5700 携帯: 090-1755-2354
メ-ルアドレス:higashiyamanomori@yahoo.co.jp
《テキストの見本》 ※(令和6年度本試験問題 問1)
問1 用地事務に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1.(〇) 国有財産法(昭和23年6月30日法律第73号)では、国有財産を行政財産と普通財産に区分しているが、行政財産のうち、国において直接公共の用に供し、または供するものと決定したものを公共用財産という。※(用地取得と補償1.1.3.(2)) 【類似過去問】 R5-1-2,R1-1-2、H28-1-2
2.(〇) 公共事業が同一地域において競合する場合(例えば国の事業と県等の事業)、各起業者が個々に同一権利者と用地交渉を行うのではなく、一方の公共事業者が他方に委託する方法を用地事務委託という。※(用地取得と補償1.1.4.(2)(ハ)) 【類似過去問】 R4-1-1、R3-1-1、H26-1-4
3.(×) 一般補償基準は、私人に対する損失補償の規範として制定されたもので、その考え方は土地収用法(昭和26年法律第219号)の定める損失補償の場合と異なる。※(一般補償基準の考え方は、土地収用法の定める損失補償の場合と「同じ」である。:用地取得と補償1.1.5(2)) 【類似過去問】 H30-5-1、H28-1-4、H26-12-1、H23-13-4、H22-13-2、H20-13-4
4.(〇) 用地取得期間の短縮を図る施策として、公共事業実施予定地における地籍調査の先行実施が考えられる。※(地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査である。用地取得期間を短縮するために、公共事業の実施予定地で「地籍調査の先行実施」を行う。:用地取得と補償1.1.6.(2)1)ⅰ) 【類似過去問】 R3-1-3、H30-1-3、 H29-1-3、H28-1-1、H23-50-2